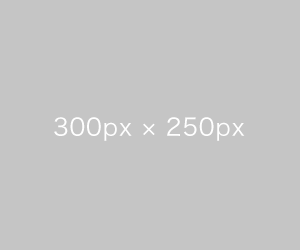現在は、建築学部の中でもインテリアデザインを専攻している。ドバイでは卒業に必要なインターンを行っており、その経験が彼女の将来観を大きく変えることになった。「会社員になるのは絶対に嫌だと思っていた」という彼女だったが、インターン先の環境があまりにも素晴らしく、考えが変わった。そのインターン先は、「ドバイで本当に1位2位を争うぐらい」の大手建築・デザイン会社だった。
日本と海外の働き方・文化の違い
時間に対する考え方と職場環境
最初に驚いたのは、時間に対する考え方の違いだった。「8時からスタートなんだけど、みんなそんなにきっちり8時に来ない」。最初は日本式に8時前に到着するよう心がけていたが、会社に着くと誰もいない状況に遭遇した。「あれ?今日休みかな?会社を間違えたのかな?」と困惑したという。実際には8時半頃までに着けば問題ないという、日本とは大きく異なるゆるやかな時間感覚だった。
ドバイの職場環境も充実していた。お弁当を持参してキッチンに置いておくと、専属のお手伝いさんが洗っておいてくれる。「本当にみんな家で仕事してるみたいな感じ」と表現するほど、家庭的な雰囲気だった。コーヒーマシン、各種お菓子、ヨーグルトなどの乳製品(4種類程度)、最近導入されたウォーキングマシンなど、これらの設備は世界的なIT企業のような働きやすい環境を提供していた。特に印象的だったのは、「たまにアーモンドミルクとか使い切っても、次に来た時にはもう補充されている」まるで魔法のような自動補充システムだった。
一方で、日本でもインターン経験があるため、両国の違いをより深く理解している。「やっぱり日本の会社とこっちの会社は違う」。最大の違いは「カジュアルさ」だと分析する。「海外の方がフレンドリーで仕事をしている」という表現で、海外の方がよりリラックスした雰囲気で仕事ができることを説明した。
食文化に見るアイデンティティの複雑さ
「何人か分からない」と語るが、食の好みは明確に日本寄りだった。「ご飯だったら完全に日本人」と断言し、得意料理についても「卵焼きを作るのはめちゃくちゃうまい」と日本料理を挙げる。最近では「チキン南蛮」を作ったというエピソードも披露し、完全に日本の家庭料理を身につけていることが分かった。

一方で、パレスチナの代表的な料理であるファラフェルについて聞かれると、「作らない」という答えが返ってきた。材料についても「パセリとか、なんか豆みたい」と曖昧な答えで、「アラビック料理は1個も作れない」と正直に語った。自分のルーツの料理にはあまり親しみがないことが伺える。
この食文化の偏りは、彼女のアイデンティティ形成において日本の影響がいかに大きかったかを物語っている。血統的にはパレスチナ人でありながら、味覚や料理のスキルは完全に日本人として育ったことを示している。
文化の違いと共通点
アラブと日本の食事マナー比較
アラブと日本の食事マナーの違いについて詳しく説明してくれた。アラブでは大皿料理で自分の前の部分だけを取る、飲み物は座って飲むのが良いとされる、男性と女性で分かれて食事することが多い、客をもてなす際は必ず2種類の飲み物(コーヒーと紅茶)を順番に出すといった特徴がある。
特に興味深いのは、客の帰るタイミングを示すサインとしての飲み物の提供方法だった。「2つ目の飲み物が出てきたら帰れる」というルールがあり、まだ1つ目の飲み物しか出ていない段階で帰ろうとすると、「まだコーヒーを飲んでいない」と引き止められるという。
「日本の方がルールが多いと思った」と分析している。箸の持ち方、お茶の持ち方、寿司を食べる時の口紅の件、座る順番、年上の人のグラスに注ぐタイミングなど、細かなルールが多いことを指摘した。
しかし、根底には共通する価値観があることも発見した。「イスラム教の教えと日本人の心がすごく似ている」。おもてなしの精神、行儀やマナーを重視する姿勢など、表面的な違いの奥に共通する価値観があることを、アラブの人々も認識しているという。「日本がイスラム教の国だったら、多分アラブよりもイスラム教らしくやるだろう」という表現で、日本人の規律正しさや礼儀正しさに対する敬意が表されている。
交通マナーと社会規範の違い
日常的な場面でも、鋭い文化比較の視点を持っている。ドバイでは「ウィンカーを出さずに割り込んでくる。ウィンカーを出す人よりも出さない人の方が多い」という状況だが、日本では「そんなことがあったらもう朝のニュースになる」という違いがある。この対比は、日本の規律正しさと海外のおおらかさを端的に表している。
学校や職場での飲食に関するルールも大きく異なる。海外(ヨルダン・ドバイ)では「基本的にいつでもどこでも食べられる。飲み食いは基本的にOK」だが、日本では厳格だ。中学時代、理科の授業中にグループワークで少しカジュアルな雰囲気だったため水を飲んだところ、「めちゃくちゃ怒られて、何をしているんだと言われた」という経験を持っている。この経験から、「暑いし、熱中症になってしまう」という現実的な観点と、日本の規律の厳しさとの違いを実感している。
父親の教えと将来への挑戦
宗教的な教えと家族の成功ストーリー
父親は非常に宗教を大切にしており、困難な時期には常に宗教的な教えで娘を励ましていた。「神様は乗り越えられる試練しか与えない」。これは父親が繰り返し言い続けた言葉で、現在でも辛い時には思い返すという。「これは試練だ。乗り越えなければならない」と自分に言い聞かせる習慣が身についている。