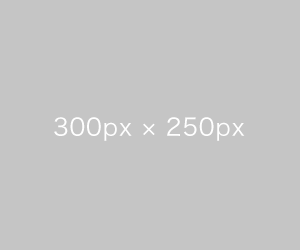爆撃の最中に生まれた少女
「私、爆撃の真っ最中に生まれたらしい」
そう語るのは、現在ドバイでインテリアデザインを学ぶミナさん。彼女の人生は、まさに波乱万丈という言葉がふさわしい。パレスチナで爆撃が続く中、両親が避難している最中に生まれた彼女の物語は、まるで映画のようだ。
父親はパレスチナの空港でエンジニアとして働いていたが、爆撃によって職場が破壊され、仕事を失った。「生き延びられるかわからない状況で、命の危険があるのに命をかけて子供を産むみたいな状況だった」と当時を振り返る。両親の勇気と決断がなければ、今の彼女は存在しなかっただろう。
そんな困難な状況の中、日本が一家を受け入れてくれたことで、新たな人生の扉が開かれた。しかし、それは同時に、まったく異なる文化と言語の世界への挑戦の始まりでもあった。
日本語ペラペラの秘密
「なんでそんなに日本語ができるんですか?」という質問に対して、答えは実にシンプルだった。「日本で育ちました」。
3歳頃から中学3年生まで、彼女は完全に日本の教育システムの中で育った。幼稚園、小学校、中学校と、日本人の子どもたちと同じように学び、遊び、成長した。そのため、日本語は彼女にとって第一言語と言える存在になった。
興味深いのは、彼女が赤ちゃんの頃のエピソードだ。肌が白く黒髪だったため、母親が子守唄で「日本人の子、眠れ」と歌っていたという。まるで予言のように、彼女は後に日本国籍を取得し、文字通り「日本人」になることになる。
貧困の中で育んだ日本での記憶
父親は大学院生として日本に来たため、家族4人は月々約10万円の奨学金で生活していた。この金額で一家4人が暮らすのは容易ではなく、貧困生活の思い出が色濃く残っている。

「本当にボロボロのところで暮らしてました。基本何も買えないので」
具体的な生活の様子を聞くと、その厳しさがよく分かる。学校で必要な文房具セットは高くて買えないため、家にあるものを引っ張り出し、足りない部分は100円ショップで補った。下敷きが必要になれば、家にある使わないファイルを切って固くして代用した。
ランドセルは中古のボロボロのものを数百円で購入。小学校に入学した時点で既にちぎれそうな状態だったという。「最初からボロボロだったから、もうちぎれてました」と苦笑いで振り返る。
食事に関しては、外食はほとんどなかったものの、両親の努力で空腹を感じることはなかった。しかし、限られた予算の中で一家4人の食事を賄うのは、両親にとって大きな負担だったに違いない。
「多分親はもっと苦労したと思う」という言葉からは、当時の両親への感謝の気持ちがにじみ出ている。
ヨルダンでの困難と成長
家庭内で両親とは簡単なアラビア語で会話していたものの、「深い話はあまりしないぐらいのアラビア語」で、読み書きは全くできない状態で高校に入学した。「本当に意味が分からないぐらい勉強しました」と振り返るように、最初の頃は試験も受けることができず、3〜4回目の試験からようやく参加できるようになった。各教科を学びながら同時に言語も習得するという、二重の困難に直面していた。
言語だけでなく、文化的な違いも大きな挑戦だった。女子校の声が大きい環境は、日本の静かな環境で育った彼女には「もう怖かった」という印象を与えた。そんな中で親しくなったのは、同じく静かな性格の生徒たち、特にドイツとのハーフの友人だった。
高校3年間、一貫して「日本に帰りたい」と思い続けていた。言語の壁だけでなく、田舎の環境も彼女には合わなかった。それでも「日本に帰るために勉強を頑張ろう」という強い気持ちが、困難な3年間を乗り越える支えとなった。
ドバイでの新たなスタートと大学生活
高校卒業後、日本の大学への進学を希望していたが、2020年に始まったコロナ禍が人生に大きな転機をもたらした。「日本がもう入国できない状態になって、書類を送るのも大変で、大学進学も困難になった」。そんな時、一足先にドバイで働いていた父親が「ドバイがおすすめだよ。コロナもほとんどないし、大学もオンラインじゃないところがたくさんある」と提案した。
ヨルダンの田舎で3年間過ごした彼女にとって、ドバイは衝撃的な都市だった。「来たらめちゃくちゃ都会で、めちゃくちゃ楽しくて、ビルも高い」。しかし、最も印象的だったのは、「しかもお寿司もある」という彼女の反応だった。パレスチナ料理のファラフェルではなく、寿司に注目したこの瞬間に、彼女の日本人としてのアイデンティティが顔を出した。